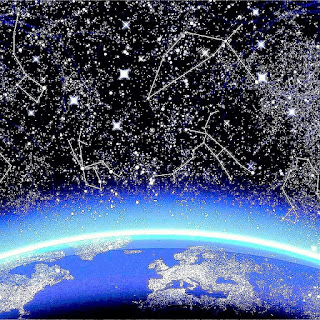『宇宙を解くパズル カムラン・バッファ著 講談社Blue Backs』
本書は典型的な数学パズル群から編成されており、シンプルな解法もあれば若干深淵な数式紹介もあるが、新書本であり概説ベースなので読み進めやすい。
とはいえ、これらの本領はあくまでも物理理論への誘いである。
本書のサブタイトルは 『「真理」は直観に反している』 とあり、全巻とおしての謎かけであろうこの言はなかなか深淵でもある。
物理現象(実在と運動)が真理であり、数学は所詮は人間なりの直感にすぎぬのか、いやいやその逆なのか…ちょっとウヤムヤ感に惑わされてしまう。
それでも本書のトータルなメッセージを僕なりに類推してみれば、なるほど数学は物理学を確立しているようではあるものの、すべての物理現象(つまり宇宙と自然)を完全に記述しきっているわけではない ─ といった由ではなかろうか。
そして物理学に対する数学の至らなさは、その’対称性’の流用において見いだせよう、とりわけ’連続対称性’のそれにおいて。
なお本書の文面読解においては、例えば「〇〇として」と「〇〇における」の論理区分などなどの難解さを留意してみたい。
とはいえ、このような論理表現上の不明瞭さは数学系の本で総じて見受けられるところではあり、しかも本書はあくまで物理学を主題に据えた概括本であるから、いちいち躓くことなく図案と数式と想像力に則って読みすすめたい。
さて、本書全体に目を通したわけではないものの、上に記したとおり重大コンテンツ(のひとつ)は序章~前段部において紹介されている「連続対称性」であろうかと察せられる。
そこで、今般の僕なりの読書メモとしてもこのあたりまでを要約雑記し、以下に記す。
※ 但しあくまでも導入部なので引用される数式も大雑把であり、だからこれらはメモ省略とする。
或る粒子が或る特定の出発点~終着点まで移動するとして、この粒子が任意に辿りうるさまざまな経路を考える。
ここで、この粒子の位置エネルギーと運動エネルギーとこれらの積分量から、この粒子の力学上の「作用」を定義する。
すると、この「作用」が最小となる経路を定義出来るはずである。
これが数学者ラグランジュに始まる「最小作用の原理」。
この原理を数学にて定式化するため、ラグランジュとオイラーは積分量の極致をもとに最小の経路を導く解法をおこし、ここで採用されたのが「変分法」。
ハミルトンは、位置の時間あたり関数と運動量の時間あたり関数を捉えなおし、これら時間微分を2次元から1次元へと単純化。
このさいに考案されたのが「相空間」で、ここからハミルトン力学が始まった。
<マクスウェル方程式~ローレンツ変換>
真空中でのマクスウェル方程式にては、磁場または電場のいずれかを力と見做した上で、ともかくも電磁波の進行とその速度を定義している。
非加速の或る慣性座標系にて、観察者がこの電磁波の速度を測定するとする。
このさい、あくまでもニュートン力学の速度合成則によるならば、電磁波とともに観測者自身も一定速度で移動しているため、両者間の「数学上の対称性」つまり「物理上の相対性」によって速度の測定値そのものが変わるはずである。
しかし、もしもこの電磁波の測定速度が観察者の移動速度にかかわらず一定であるとすると…
ローレンツは、マクスウェル方程式においてニュートン力学とは異なる「数学上の対称性」が在る由を指摘。
電場、磁場、粒子の位置、および時間が、或る座標系から別の座標系へと移る場合にどのように変化するかを数学にて導き、そこであらゆる座標系にて同じ形をとる方程式を導出。
これが「ローレンツ変換」の数学。
マクスウェル方程式とローレンツ変換を元に、アインシュタインは在る物体粒子とその質量と光速2乗がこれら物理エネルギーと等価になると導いた。
これは電磁気に留まらぬ「時空全般の相対性理論」となった。
リーマンは、歪曲した時空においても重力場の自由落下の経路は直線を辿ると指摘、これが「リーマン幾何学」。
これによって「一般相対性理論」は完全に幾何学的な重力理論となった。
<量子力学>
シュレーディンガーは、或る粒子のエネルギー演算子と運動量演算子と位置エネルギー演算子と質量をもとに、「量子力学の方程式」を編み出した。
アインシュタインの「特殊相対性理論」とはエネルギーの次数が2であり、シュレーディンガーの「量子力学方程式」はエネルギーの次数が1である。
この両者のつじつまを合わせようと、ディラックは「行列数学」を投入して次元を統一する方程式を表現した。
かつ、この行列数学は位置や運動量とは独立した電子自身の運動の自由度をも表現、こちらが「スピン」である。
ただし、ディラック考案のこの行列数学の方程式では、電子の正エネルギーも負エネルギーもありうることとなる。
ディラックの解釈によれば、負のエネルギー状態を成す'電子群の海’が存在しており、一方ではパウリの排他原理も働くことにより、エネルギー準位軌道と電子のエネルギー状態の相関をともに説明はかった。
一方で、アンダーソンは宇宙線における電荷粒子の軌跡を観測し、陽子とは別の正電荷を有する「陽電子」を発見。
<場の量子論~経路積分>
ここまで組み合わせて考えると、あらゆる粒子(量子)は移動経路を1つに特定しようがなく、あらゆる経路を進んでいることになる。
ここで、それぞれの経路に位相の複素数を割り当ててみれば、これら位相の総和と移動経路の選択確率が比例関係にある ─ と解釈することになり、これが「場の量子論」。
こうなるとラグランジュやオイラー以来の「最小作用の原理」のみでは説明しきれなくなる。
ファインマンは、或る点から別の点へと移動する粒子のとりうる各経路に「作用」の指数関数を’重み’づけて、これら経路と時間の選択確率を導いた。
ここでの確率計算は、経路と時間の積分にて複素数を採用しこれを2乗しつつ、さらにプランク定数を充てこんだもので、この換算プランク定数が0となる極限のもと、変数が無限個の無限次元における積分計算を為す。
これがファインマンによる「経路積分法」であり、シュレーディンガーの量子力学を新たに定式化しつつ、またニュートン力学をラグランジュとオイラーの形式で表現しなおすことにもなった。
しかしながら、ファインマンの「経路積分法」をマクスウェルの電磁気理論に充て込むためには、あらゆる電場と磁場の無限次元空間を設定しつつ積分計算を行わなければならず、これはあまりに複雑すぎるため完全には為されていない。
つまり、「場の量子論」の数学上の完全な定式化は未だ実現されていない。
数学上の定式化が為されていないのだから、物理法則の定式表現も為されていない。
===============
<物理上の連続対称性 ─ その破れ>
ラグランジュとオイラーとローレンツ変換にては数学上の対称性が大いに活かされてきたが、かかる対称性をとくに物理現象に充てこんだものが「連続対称性」である。
この物理上の「連続対称性」を集約すれば;
・時間反転における連続対称性
・空間内での鏡映パリティとしての連続対称性
・荷電共役変換としての連続対称性
そして、1つの連続対称性に応じて必ず保存則が1つは成り立っており、これが「ネーター」の定理。
時間の並進における連続対称性からはエネルギー保存則を導出可能であり、また空間の並進における連続対称性からは作用/反作用と運動量保存則が導出可能、そして回転における連続対称性からは角運動量保存則が導出可能。
「ローレンツ変換」においては、4次元時空内にて空間が時間方向へ、そして時間が空間方向へと連続対称性を成している。
そして「相対性理論」と「量子力学」の組み合わせとなると、上の3つの連続対称性すべてが成立しきっている。
(宇宙はビッグバンと相転移とその後の燃焼拡散が一方向なので、時間反転の連続対称性は成り立っていないともとれるが、しかし宇宙が拡大と収縮を繰り返していると見れば時間反転の連続対称性が成立している。)
しかしながら、宇宙自然のすべてが連続対称性を成しているわけではなく、むしろ連続対称性を破ってこそ成立してしまった(とも解釈しうる)物質も現象も多い。
何らかの複数の粒子を近接させると、それらの粒子の電子スピンはすべて上向きあるいは下向きの同方向のスピンと成り、ゆえにこれらの系のエネルギーは基底状態にて最小状態に収まっている。
この系が或る一定の温度条件下に在ってこれら粒子が温められると、温度変化に応じてそれぞれの電子スピンの方向が’確率的に’変わる。
この確率上の相関はボルツマン定数を以て数学表現されており、これが「ボルツマン則」、かくて連続対称性は成立してはいる。
ところが、磁石を極低温におくと、それら粒子の電子スピンは上下どちらかの方向を向いたきりとなってしまい、温度条件の変化に応じていないことになる。
こうなると「ボルツマン則」は通用せず、連続対称性は無い。
あらゆる剛体は、外部から加えられた一定方向の力に応じて構成原子が特定の位置を占め続けてしまい、だからこそ剛体そのものがその方向に一緒くたに動いてしまう。
つまり、この剛体は(構成原子は)並進対称性を破っていることになる。
ボルツマン則の着想にのっとり、宇宙のビッグバンと相転移、そこにおけるヒッグス場の生成、そこでヒッグス粒子が為す質量獲得などを俯瞰すれば、この超スケールのプロセスは連続対称性を破っていることになる。
===============================
… ざっとここまで、本書巻頭箇所のほんの一端を紹介したに過ぎないが、それでも物理学の総復習ないし総括を楽しめるものである由、お分かり頂けるのではなかろうか。
ともあれ本書は見かけ以上のスケール感満載、次から次へと物理論題が目白押し。
そしてどれもこれも切り口は数学パズルであり、変人の多い数学ファン連中をもけして退屈させない思考鍛錬の書たりえよう。
以上